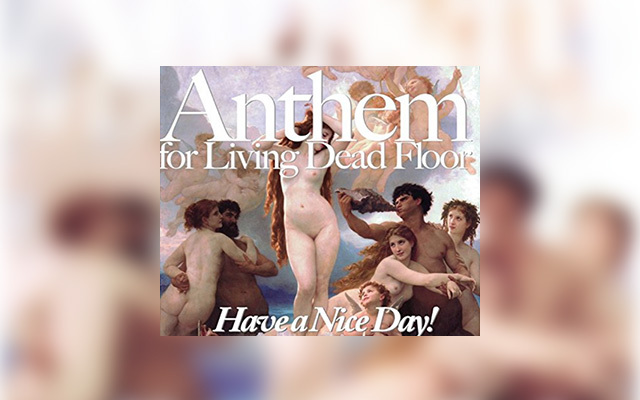
Have a Nice Day!(ハバナイ)を初めて聴いたのは4月のはじめ。
それからこの一ヶ月間は、「ハバナイ中毒」といっていい程どハマりしていた。
4月末には期間限定で無料公開されたドキュメンタリー映画「モッシュピット」を鑑賞。
5/1にはフリーLIVE(@Zepp DiverCity Tokyo)にも参加できた。
その濃いハバナイ体験の中で、色々と新鮮なインパクトを受けたし、考えたこともあった。
ライブも観戦したことだし、このタイミングでつらつらとハバナイについて書いてみたい。
(と、何も考えずに書き始めたら、想像以上に長文に…(約8千字)。
あと、「売れてない」現状についての感想が多めになっている。)
ハバナイを知るごとに受けたインパクトの数々
初めて聴いたベスト「Anthem for Living Dead Floor」
ハバナイを聴いたキッカケは4月に開催された音楽フェス「SYNCHRONICITY」の全出演者をapple musicでチェックしていた時。
ハバナイもclubasiaステージに出演していたので、ベスト「Anthem for Living Dead Floor」を聴いてみた。
一曲目では「お、いい感じ」くらいの印象だったが、曲を重ねるごとに中毒成分が浸透。
ラスト「SCUM PARK」を聴き終える頃には完全にハバナイ中毒に陥っていた。
個人的には「SCUM PARK」に一番オリジナリティを感じる。
キラキラしたシンセポップ自体に目新しさはないかもしれないが、「SCUM PARK」の【リフレインする激しいシャウト×けだるそうなメロウなボーカル】という混沌とした調和っぷりは、ちょっと他に思い浮かばない。
のちに知ったところでは、このベストはレーベル移行後に名刺代わりに作ったとのこと。
全アルバム聴いた中でも、一番完成度が高くビギナーにも最適な一枚だったと思う。
ある意味衝撃だったyoutubeの再生回数
映像として初めて観たのは「NEW ROMANCE」のMV。
この時のハバナイのイメージは、「すでに相当売れてるバンド」。
フェスに呼ばれてるくらいだし、何より一発でハマった音楽なので、当然そう思った。
ベストには収録されていない「NEW ROMANCE」も文句無しに最高だった。
「ルー・リードのTシャツ着てキレキレに踊ってるオッサンは一体?」
とさらなるインパクトがあったが、それ以上に驚いたのが、再生回数。
3万未満…??
あまりの自分の印象との落差に目を疑う。
最近の曲だから? いや、アップは2年以上前。
非公式の動画だから? いや、レーベルの公式MV。
それからインタビュー記事や映画「モッシュピット」で、「突き抜けられない」現状への言及を目にすることになる。
冷静に考えるとその理由らしきものはあれこれ浮かぶけど、それにしても3万…。
大森靖子とのコラボ曲でも再生回数7万…。
数百、数千の動画もザラにある。
この一ヶ月間、ハバナイのことがグルグル頭を巡っていたのは、「なんでこんなに売れてないんだ?」という消化不良の疑問があったことも大きい。
ハバナイのライブ風景も予想外
次に見たのが代表曲「フォーエバーヤング」のライブ動画。
ここでまたライブ風景の意外さに驚く。
曲調や歌い方から、もっとユルい感じを予想していた。
出演したフェス「SYNCHRONICITY」もモッシュやダイブのイメージはない。
でも、ライブを見るとやたら激しい。
音源とは全然テンションが違う曲。
フロアでガンガン起こるモッシュとダイブ。
(↑の動画ではそこまでではないが)
かといって、一般的なロックファンとは違う客層。
というか、どんなファン層か掴めない。
そして、このヨレヨレのTシャツ着たオッサンは一体誰なんだ?
(あとで知ったが、今は在籍していない内藤さんというパフォーマー兼vocalだった)
曲と同様で、「何か違う」印象で、さらに興味がわいた。
そして、改めて思う。
音源も良いし、ライブもキッチリ沸かせているのに、なんでハバナイは跳ねないんだ?
(生歌はだいぶ下手だけど)
クラウドファウンティングでの浅見北斗のコメントを読んで
ハバナイはクラウドファウンティングで集めた300万円で5/1にZepp DiverCityでフリーライブを開催した。
その中でvocalの浅見北斗が次のようなコメントをしている。
Have a Nice Day!(ハバナイ)、最新リリースとフリーパーティー概要
ここ2年ほど、オレたちは最高だと感じる瞬間を何度作り出せただろうか?
〜
いなくなったヤツや、続けることができなかったヤツの屍を尻目にオルタナティブな闘争を続けていることはまことにもって天晴れと言うべきだろ?だが悲しいことにオレが思い描いた素晴らしいことは起きなかったよ。そして今後もそれが起きることはないだろう、ということがオレにも分かってきた。先進的な革命めいたものが起きることをロマンチックに妄想してたのだが、どうやらわれわれのような歪な存在は”彼ら”の世界にはあまりフィットしていないようだ。
「だが悲しいことにオレが思い描いていた素晴らしいことは起きなかったよ。」
ちょうど自分が「なんで売れてないんだ」と感じていたので、このセリフはすごくタイムリーに響いた。
失望感と無念さが(もしかしたら本人が意図した以上に)伝わって、自分のことのように共鳴してしまった。
浅見北斗が妄想した「先進的な革命めいたもの」は自分の中では起きていた。
はじめて聴いた時、そういう現象を起こしているバンドだと「錯覚」した。
「Anthem for Living Dead Floor」はハバナイという存在形態で生み出せる一つの頂点だと感じる。
「それでこの程度の反応なら、もう無理じゃね」
ファン歴1ヶ月の自分でもそう思った。
それでもまだ、もっと届いていい、届くはずだ、とも思っている。
映画「モッシュピット」
「モッシュピット」はハバナイ中心に「東京アンダーグラウンド」シーンの活動を追ったドキュメンタリー。
ハバナイの他にNATURE DANGER GANG、おやすみホログラムが出演し、zepp同様、クラウドファウンティングで募った資金で開催した2015年の恵比寿リキッドでのフリーライブの様子が描かれている。
Zeppライブの前に数日間無料配信していたので自分はそれを鑑賞した。
本編とは別シーンが結構含まれている「プロローグ Web版」は期間関係なく公開されている(↓動画あり)。
決して負けない強い力とは一体なんだろう?
この作品で印象的なのはインタビューのシーン。
浅見が「(今までのライブよりもっと)普通じゃない風景を」と感極まるところだろう。
(29:20〜)
インタビューのあと、浅見のモノローグが続く。
「『決して負けない強い力』とは一体なんだろう」と自問し、「オレは最近それが『信じる』ってことなんじゃないかと思ってる」と自答。
「決して負けない強い力」とはブルハの「リンダリンダ」の一節。
浅見はインタビューでもブルハの影響を公言していて、意外な気がしつつ、そこもシンパシーを感じたポイントだった。
ブルハ好きだとしたら浅見は他にも意識してる歌詞があると予想する。
マーシー作詞作曲の「泣かないで恋人よ」
「どでかいウソをつきとおすならそれは本当になる。」
もしくは同じくマーシーの「うそつき」
「100億もの嘘をついたら今よりも立派になれるかな。
下手な嘘ならすぐばれて寂しくなっちゃうよ。
せめて100年はばれない たいした嘘をつく」
2015年のキャパ1000人のリキッドは3組でほぼ埋められた。
2018年のキャパ2500人のZepp Tokyoではワンマン(大森靖子が一曲だけ登場)でフロアはまだ余裕がある状態だった。
そんな見通しは明るくない状況で、浅見は「次は横浜アリーナ(キャパ1万7千)」とまた「ウソ」をついた。
ぜひ、そのウソが突き通せるか見届けたい。
(ライブでは「横スタ」と言っていたが、後日浅見がツイッターで訂正していた。)
自ら作った虚構に戦いを挑むドン・キホーテ
映画の冒頭では、音楽フェスの風景が流れ、大きな利益をあげているというナレーションが流れる。
フェスの巨大なステージはハバナイが辿り着きたいゴールというより、倒すべき敵のように映る。

映画「モッシュピット」 冒頭のシーン
映画を見終わった時、そのシーンは風車を巨人と思い込み、戦いを挑むドン・キホーテを彷彿とさせた。
そして、ブルハが引き合いに出されたので、一つ対比的に思ったことがある。
ブルハの音楽も大人的なものに対するカウンターとして機能していた。
ただ、ブルハの時代は世の中が今よりずっと権威的で、抑圧的な力が幅を利かせていた(と思う)。
そして、ヒロト達も純粋に生きにくさや不安に苛まれる若者だった。
つまり、敵は仮想ではなく、現実的なものであり、それを指す言葉も「世の中・大人」とストレートなものだった。
浅見の音楽には「バビロン」や「ディストピア、ロマンス、ゾンビ、東京アンダーグラウンド」といったフレーズが繰り返し用いられ、独自の世界観を築いている。
浅見の場合も、「バビロン」が象徴するメジャーなシーン、資本主義的なものに釈然としない思いがあるのは本心だろう。
でも、浅見の場合はすでにいい大人で、十分俯瞰的にもなれ、消化できるように思う。
つまり、半分はリアル、でももう半分は意識的に敵に仕立て上げ、自ら作った敵に戦いを挑んでるような趣を感じる。
なかば遊び感覚のように。
だから「ブルハに比べると強度が弱い」という話ではなく、虚構/言葉を作ることで現実的な強度を生み出しているのだと思う。
「モッシュピット」もその作用の一つではないだろうか。
「ハバナイの曲にモッシュのイメージはなかった」と書いたが、実際は想像以上にモッシュを生み出していた。
それは「モッシュピット」という言葉を前面に打ち出し続けることで、ファンの意識を喚起し、現実化させたものなんじゃないだろうか。
(ライブにはよく行くが、モッシュピットなんて言葉ハバナイ以外で聞いたことない)
NATURE DANGER GANG
ハバナイもインパクトがあったけど、この映画で知ったNATUREもスゴかった。
これ、元ネタはどれだけ認知されてるんだろう?
サビがまんま「笑う犬」という番組で原田泰造とホリケンがやってたコントの歌。
当時大好きだったコントが、10数年の時を経てよく分からないバンドがよく分からない歌に仕上げて、フロアを揺らしている。
たった数年前に、日本にこんなノリだけで成立しているバンドが存在していたことに感動すら覚えた。
(NATUREは2017年に活動休止)
おやすみホログラム
おやホロは今も活動中のアイドルで、彼女たちもこの映画で知った。
NATUREは「笑う犬」を彷彿とさせたが、おやホロは「世界の終わり」という曲名があったり、浅野いにおの漫画みたいな雰囲気。(「おやすみプンプン・虹ヶ原ホログラフ・世界の終わりと夜明け前」)
ハバナイとの関係は浅見北斗が「エメラルド」という曲を提供して、コラボしている。
「エメラルド」も音源はセンチメンタルな感じなのに、ライブだと全然別物。
NATURE に負けず劣らず弾けていて、初めて見た時は「アイドル」と認識できなかった。
ハバナイをはじめ、NATURE、おやホロ、そのファン達も、とにかく既定のジャンルやカテゴリーで捉えにくい。
だからこそ「東京アンダーグラウンド」というシーンを指す言葉に説得力があるのだろう。
Zeep DiverCityでのフリーライブ
ハバナイ漬けの一ヶ月の総決算とも言えるライブだけど、感想はあっさり目に。
肝心のモッシュピットに入れなかったし。
この日のライブは「安全性への配慮から、最前のモッシュピットに入れるのは5000円以上投資した人だけ」という措置が取られていた。
柵はモッシュピットの境界以外にも多めに設置されていたと思う。
この措置に対しては、なくても良かったのでは?とも思うが、無責任なことは言えない。
でも、今後はあえて設けないんじゃないかという気はする。
やはり他のロックバンドとは一味違ったライブ模様
開演前はSEではなく、DJがプレイした音楽が流れていた。
(DJは「モッシュピット」にも出演しているDJ April)
DJの演奏は初体験。
楽器の音じゃなく電子音だからか、耳にキンキン響いてやたら音がデカく感じた。
そして、遅めに到着したのに、ロッカーは全然埋まってないし、ほとんど誰も首にタオルを巻いてない。
ライブ中はみんなバシバシ撮影しているし、vocalからもファンからも野次が飛ぶ。
やっぱ普段行くロックバンドとは違うな、と異文化に紛れ込んだ気分になった。
浅見北斗の生歌への不安が払拭
この日、一抹の不安を感じていたのは浅見北斗の生歌に対して。
歌が上手くないのはyoutubeで知っている。
でも、歌が下手なのに「何故か人に響く、音の中で映える」vocalもいる。
stone rosesやnew orderみたいに。
逆に普通に下手な場合もあって、ハバナイの場合はどうなんだろう、と。
ガッカリしたらこれでライブは最後かなと、期待半分、不安半分でライブ開始。
感想はお世辞にも上手いとは言えないけど、お世辞ではなく「良い声」だと思った。
次はちゃんとお金を払ってまたライブに行きたい。
なぜか大森靖子の歌で涙
後半、コラボ曲「Fantastic drag」で、大森靖子が登場。
彼女は特に思い入れの強いアーティストではない。
が、歌がはじまるといつの間にか涙が流れていて自分自身驚いた。
なんの涙かもサッパリわからないが、ともあれたった一曲で意識をもってかれたということで。
「大森靖子、アーティストだなー」と実感させられた。
お金回収ボートに乗りこむアドリブも天性のものを感じるし、大森が札を手渡される一方、ステージで小銭を投げつけられる浅見、という対比も最高だった。
どこまで本気かわからない浅見のMC
何度か触れているが、浅見の言葉はどこまで本当かわからないところがある。
一曲目終わった途端、MCが「お前ら気合が全然足りてない!」。
「ライブはここまで。こっからはアンコール」とまで言う。
自分は普段のライブを知らないので、純粋に不満だったのか?それとも意図的な煽りやユーモアか?
最終的に「今日は本当にアンコールはなし」となったのも、フロアの温度に不満だったからか?それとも事前の決め事だったのか?
動員は満点ではないにしろ、実際Zeppのライブに対して浅見の評価はどうだったのだろうか。
最後まで見えなく、今も気になっている。
クラウドファウンティングで目標額達成したのに、「金ない金ない」と連呼してたのも、ガチなのか半ばジョークなのか。
ガチなら、観客の上にゴムボート流して回収っておかしくないか。
自分もそこまで言うならと払う気満々だったが、全然ボートに届かず。
どう考えてもそういう人が沢山いただろう。
生で見た浅見北斗もどこまで本気かわからない人だと改めて思った。
ハバナイのセルアウトへの壁
すでに「こんな長文誰が読むんだ」という気分になってるが、最後にハバナイの売り方について思うことをいくつか。
「セルアウト」とは「売れること」。
一般的には「自分を捨て大衆に迎合。商業主義にはしる」というマイナスイメージの言葉かもしれないが、映画「モッシュピット」内で単純に「売れる」という意味で使われていたので、その意味で使っている。
ジャンルが見えないのは大きなビハインド
商品を売る場合、ニーズやターゲットを絞るのが商売の基本で。
規定のジャンルにわかりやすくハマった方が、そのジャンルのファン層に届いて拡大しやすい。
ハバナイはやっぱりジャンル的にカテゴライズしにくいのが、まずネックになってるポイントだろう。
それはそれだけニッチにならざるおえない、市場に届きにくい、ということで。
この点はどうしようもないので、「分が悪い戦いだな」と思うばかり。
「届ける」ことへの意識について
当然ハバナイの活動全般からは「できるだけ多くの人に」という気持ちを感じる。
でも、どこか「届く人にだけ届けばいい」というスタンスも感じる。
例えば、アートワーク。
実は、曲を聴く前から↓の画像などはネットで何十回も目にしていた。が、全てスルーしていた。

出典「ハバナイ、小室哲哉へのリスペクト捧げる「WOW WAR TONIGHT」カバー | ナタリー」
Web制作をやってる身としては、デザインは「一瞬で初見のユーザーの気持ちを掴めるか」を意識して作る。特に広告的なビジュアルは。
その視点でみると、ハバナイのアートワークは「もったいない」と思ってしまう。
確かにハバナイの音楽を知ってる人には味があるし、クオリティも高い。
でも、ネット、SNSで初めて見た大多数の人にとってキャッチーとは言いがたい。
そこに「伝わる人にだけ伝わればいい」というインディーズっぽい精神を感じてならない。
浅見はコメントで「先進的な革命めいたもの」と書いていた。
革命はマスとコア両方に届いて起こるものだと思う。
だとしたら、アートワークひとつとっても「一人でも多くの人に届ける・最大公約数的に洗練されている」ことにもっとシビアになるべきではないか。
と書きながら、すごくつまらない物言いをしている気分になってきたが、、
少なくとも他媒体のアートワークとは別にWebで使うビジュアルはもっとクリック率を意識してもいいように思う。
声の特性を最大限活かす曲作りを期待
自分は歌モノの曲は「vocalのもつ声の特性を活かすテイスト」かどうかが重要だと思ってる。
ヤーヤーヤーズのカレン・Oが「自分の声は楽器だと思っている」と言っていたが、ライブで実感したのは、浅見の声はメロディを奏でる楽器ではなく、リズムを刻む楽器のようだ、ということ。
メロディもいいけど、真骨頂はリズムを刻むものとして機能した時だと感じた。
繰り返すけど、特にライブの場合は。
「マーベラス」よりも「ゾンビパーティー」。
「blood on the mosh pit」よりもや「フォーエバーヤング」。
足を小刻みに動かすダンスのように、ラップやシャウト、弾けるような歌い方の時の方が力を発揮しているように思う。
これは余談だが、例えば、きのこ帝国。
メジャーデビュー時の音楽性の変化に対して、それこそ「セルアウト」と指摘があったが、個人的に気になったのは声と曲との相性だった。
自分は佐藤千亜紀の声は明るく柔らかい曲より、ダークで激しい曲の方が活きると思っている。
(「猫とアレルギー」より「海と花束」がハマってるということ。)
だから、「辺境のジャンルからポピュラーミュージックへの変化」という視点ではなく、「声質を最大限活かす曲から、真骨頂とは言えない曲への変化」と捉えている。
どう音楽性を変化させたとしても、それが「声を活かした曲」なら何も問題はない。
ハバナイに話を戻すと、「最近はテンポが遅い曲が良くなってきた」みたいなコメントをどこかで見た。
でも、リズムとして声をのせる曲も、つまり「フォーエバーヤング」と同じ方向性で「フォーエバーヤング」を超える曲作りも期待したい。
さいごに
この一ヶ月間、本当にハバナイばかり聴いていた。
同時に「なんで売れないんだろう?」と引っかかっていたので、この機会に思ったことをまとめて書いてみた。
この文章を書くのもそこそこ時間かかっていて、「なんでこんなハバナイについて考えないといけないんだ?」とすら思えてくる。
そして、一周回って、「売れないなら売れないでいいんじゃないか」とも思っている。
むしろ、ずっともがいてる姿が、そんなストーリーが続いたら、それはそれで面白そうだ。
今度は横浜アリーナで1万7千人の観客を前に、「金が全然足りてないんだ!」と嘆く浅見北斗の姿を見てみたい。

コメントフォーム閉鎖中