
「青いカナリア」はジッタリンジンの10枚目のシングルで、アルバム「BANZAI ATTACK」にも収録されている。
2019年には公式チャンネルでライブ動画も公開されていて、ファンの間でも人気の高い一曲だ。
この記事では歌詞の内容から自分が考える「青いカナリアが名曲である理由」について書きたい。
はじめに身もふたもない事を言うと、曲において歌詞の重要度はそこまで高くない(と思う)。
少なくとも曲の印象を占める割合は歌や演奏の方が大きいだろう。
そもそも、実を言うと自分は長いこと「青いカナリア」の歌詞を意識していなかった。
それでも、最初からハマったし、名曲だと思っていた。
ただ、歌詞を意識した後は曲の聴こえ方も変わったし、さらにスゴい曲だと感じるようになった。
そして、その背景には「分裂」というキーワードが見て取れるんじゃないかと思う。
この「分裂」と言う表現は、スピッツを分析した下記記事を参考にさせてもらった。
記事では「分裂」という視点を元に「スピッツが愛される理由」を論じている。
(おそらく、「分裂」という考え自体は筆者の「発見」ではないと思われる)
記事でも書かれているように、「分裂性」はスピッツの専売特許というわけではない。
様々な優れたポップミュージックに潜んでいて、意識的・無意識的に力を発揮している。
そして、その「分裂」はジッタリンジンの曲、とりわけ 「青いカナリア」にも見られる、というのがこの記事の主旨である。
「青いカナリア」の歌詞と初めて歌詞の内容を意識したキッカケ
自分は最初に「青いカナリア」を聴いてからずっと歌詞の内容を意識してなかった。
意識してなかったというより、もっと言うと、かなり誤解をしていた。
曲調はテンションが高いロックチューン。
「突き抜ける空に」と言う一部の歌詞だけ耳に残り、歌詞も明るいハッピーな歌だと思っていた。
「青いカナリア」は「(幸せの)青い鳥」的な感じかなと。
そんな中、歌詞を意識するきっかけはダイナ・ショアの「Blue Canary」。
この曲は哀愁漂う1950年代の曲で、タイトルの「Blue Canary(青いカナリア)」という歌詞から始まる。
ジッタの作詞作曲を手がける破矢ジンタからはしばしば5、60年代の音楽の匂いを感じるので(憶測を多分に含む)、「もしかしたら、『青いカナリア』ってこの曲名からかな」と思っていた。
ただ、ダイナ・ショアを聴いて思ったのはそのくらいで、ハッとしたのは、その後雪村いづみが歌う「Blue Canary」の日本語カバーを聴いたとき。
雪村いづみの「Blue Canary」も物悲しいムードは原曲通りだが、歌い出しが次のように歌われている。
「寂しいカナリア」
この時、初めて「Blue Canary」の「blue」は色の「青」じゃなく、「bules(ブルース)」の「blue」。
つまり、「憂鬱、悲しい」だったと分かる。
それで、「もしかしたら」とジッタの「青いカナリア」の歌詞を確認。
そこで初めて実はすごく憂いを帯びたアンハッピーな歌詞だったと気づく。
Cause I love you, don’t go away
突き抜ける空に
Blue Canary 飛んだ
またひとりぼっち〜
あの日二人 占っていた
遠い未来 恋の行方
何度やっても うまく行かずに
泣き出したね
I Iove you,love you,love you,beby
時間差で歌詞の内容に気づいたこともあって、とりわけ曲調とのギャップについても考えさせられた。
こんな悲しい内容なのに、なんでこんなに明るい曲なんだろう。
こんなにギャップがあって矛盾してるのに、なんで一つの曲として成立しているんだろう。
いや、こんなに矛盾してるのに成立してるからこそ、名曲なんだろうか?
「またひとりぼっち」という描写と、カナリアが青空を突き抜ける情景は一見明らかに矛盾する。
でも、歌詞をちゃんと意識して聴いても、感じるのは違和感ではない。
むしろ、ただ「楽しい曲」という以上に、よりなんとも言えない余韻を残し、曲としての厚みも断然増したように感じる。
スピッツの歌/優れたポップミュージックが内包する「分裂」とは
詳しくはリンク先参照。
スピッツはなぜ「誰からも愛される」のか〜「分裂と絶望」の表現者 | 現代ビジネス | 講談社
自分なりに要約すると、
スピッツの楽曲には〈陽と陰〉、〈希望と絶望〉、〈陶酔と覚醒〉、〈非凡と平凡〉、〈現在と非現在〉、〈可能と不可能〉といった、あらゆる分裂・対極要素が詰め込まれている。
この「ギャップ」は色んな要素の中に存在するが(歌と演奏の印象など)、とりわけ記事内で注目しているのは歌詞。
草野マサムネの伸びる高音によって、コーラスに入ると同時に「だ」の「a」の母音が広がったときの開放感はすごい。しかし、昇天するような解放が表現された瞬間に、その背後で鳴る和音はF#mの悲しみへと向かい始める(F#mは「マイナーコード」であり、これは一般的に悲しみや暗さを表現しやすい)。悲しみと喜びが楽曲の中で分裂しているのだ。
考えてみれば、コーラスの手前には「ありふれたこの魔法」という、〈平凡(=ありふれた)〉と〈非凡(=魔法)〉に引き裂かれた表現が登場するし、冒頭部の「新しい季節」からはじまる一節は、〈新しい〉にもかかわらず「君を追いかけた」と〈過去形〉で終止する。かくのごとく、『ロビンソン』にはいくつもの「分裂」が織り込まれている。
音楽は元々、私的な営為であり、同時にポップミュージックは公的な営為である。
凡百のポップソングは「公的」に偏る、あるいは「私的」の域を出ない。
優れたポップミュージックは「公」かつ「私」という両義性を獲得し、大量生産の商品であると同時に、固有の芸術作品たり得る。
スピッツの音楽は「分裂性」を内包していることで、「優れたポップミュージック」となり得ていて、だから「スピッツの音楽は誰からも愛されている」。
おおむねそんな風にまとめられると思う。
記事を読んでちゃんと理解できなかった点
少し話が逸れるが、記事を読んで、
なぜ「分裂性=対極要素」を内包することが、「<公>と<私>の間にブリッジ」をかけ、「大量生産品かつ芸術作品=優れたポップミュージック」に繋がるのか?
という点はすっきり理解できなかった。
なぜ、スピッツの【「ありふれたこの魔法」という、〈平凡(=ありふれた)〉と〈非凡(=魔法)〉】みたいに、表現が対立・分裂してると「公/私」の両義性を獲得するのか?「大衆性」も「エゴ」も捨ててないことになるのか?
と、改めて考えると、なんとなく分かるような気もしつつ「うーん…」となる。
つまり、
「分裂性している」→「理由」→「優れたポップミュージックである」
の「理由」の部分はうまく飲み込めなかった。
一応ここでは「記事内容を理解できなかったところもあった」という点を補足。
記事を読んで理解・同意できた点
途中の「理由」は理解しきれてないけど、結論はすごく納得できた。
結論というのは、
「優れたポップミュージックである」→「分裂している」
という指摘自体のこと。
「優れたポップミュージック」は確かに「分裂性」を内包している(ことがよくある)。
そういう点で、スピッツは「ポップの極北」であり、それが「スピッツがライトな音楽ファンから熱心な音楽ファンまで多くの人に愛される理由」というのも理解できた。
「青いカナリア」をはじめ、ジッタリンジンの曲も「分裂」を含んでいる
ここまででもう言いたいことは伝わってると思う。
ジッタの「青いカナリア」も暗い影を落とした歌詞と底抜けに明るい曲調というギャップがある。
歌詞の中でも「突き抜ける空に」「またひとりぼっち」をはじめ、相反する要素がある。
昨年スピッツの記事を読んで、「青いカナリア」もこの「分裂」というキーワードが当てはまると思った。
そう考えて見渡してみると、他にもジッタの曲には「分裂」が含まれる曲が少なくない。
全体的に明るくてノリがいいイメージがあるけど、よく聴くと憂いを帯びている曲がいくつも思い浮かぶ。
「プレゼント」「夏祭り」「Don’t let me down」「知らない街へ」「市営プール」「クローバー」
そんなジッタの曲の中でも、最も歌詞と曲調のギャップが激しい、「分裂の強度」が高いのが「青いカナリア」ではないだろうか。
「大好きな人に去られて、またひとりぼっち」という最悪の絶望感と、一羽の鳥が青空を突き抜ける最高の開放感。
(「blue canary 飛んだ」を「悲しみのカナリアが飛んだ」と捉えると、この一文だけでこれ以上ない強い分裂性を含んでいるし、歌詞の奥深さや想像の幅もグッと広がる。)
そんなこの上ない「分裂」が、「青いカナリア」をジッタの中でも屈指の名曲にさせているのかもしれない。
さいごに。
自分が考える「分裂」が作品をグレードアップさせる理由
自分が素朴に思うのは「シンプルに深みが増すから」。
それはひいては「創作の難易度が上がり、必要な表現力もグッと上がる」ということ。
例えば、「突き抜けるような楽しさ」をテーマに曲を作る時、普通は歌詞もメロディも楽しい感じに作る。
そうすると、一つの作品として成立させやすい。
が、一方で表面的で面白みに欠けてしまう。
かといって、ひねりのある深みのある表現をしようとすると、そう簡単には成立させられない。
そこがきっと創作の一筋縄ではいかないところ。
「分裂を盛り込めばOK」と意識すれば簡単に実現できるものではない、という気がする。
一見矛盾する要素を盛り込んで、一つの作品として成立させ、なおかつ人の心を動かす。
その創作過程の中には、どこまでいっても言葉で分解しきれない、ある種のマジックめいたものが潜んでいるように思う。
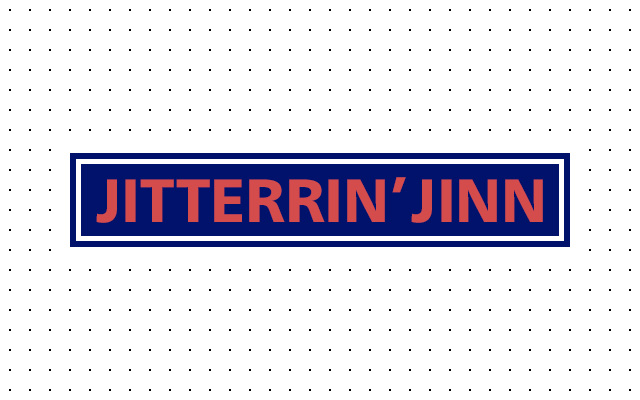
コメントフォーム閉鎖中